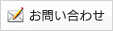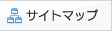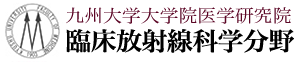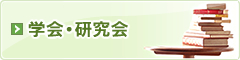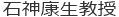
九州大学放射線科のホームページをご覧くださって、ありがとうございます。令和2年(2020年)4月より、教授に就任した石神康生です。コロナ禍第一波の頃に教授に就任して早くも5年が経ちました。 この5年間でコロナ禍もほぼ収束しましたが、この間に当教室に約40名の新たな仲間が加わりました。また、当教室から7名の教授も誕生しました。
先ず、簡単に自己紹介をさせていただきます。私は熊本県出身で、平成7年(1995年)に九州大学を卒業し、九州大学放射線科とその関連施設で画像診断医としての修練を積みました。米国アイオワ大学放射線科に2回留学し、 計5年間スタッフとして臨床に従事しました。また、教授着任前の1年9か月間は琉球大学放射線科に勤務しました。九州大学放射線科は昭和4年(1929年)に開講した伝統ある教室であり、私は6代目の教授になります。
放射線医学は画像診断と放射線治療(放射線腫瘍学)の二つの分野に大別されます。九州大学放射線科も開講当時は放射線治療学講座としてその歴史をスタートし、現在も画像診断医と放射線治療医とが一緒に教室を運営しています。 そして当教室では、内視鏡診断・治療も行っています。私は画像診断医と放射線治療医が一緒に教室運営を行っていることを教室の強みとして生かし続けていきたいと考えています。 また、内視鏡診断・治療は放射線科としては異色かもしれませんが、医局員の進路選択の幅を広げています。
当教室には、二代目教授の入江英雄先生の「荊棘の道と知りつつわけ入りし この荊棘の道を愛したまひき」という書が飾られています。これは、教室を開講した初代教授の中島良貞先生に思いをはせ、後発の診療科の困難な道のりを「いばらの道」になぞらえ、 新たな放射線医学という道を切り開く気概とその道への愛着を表したものです。また、入江先生が残されたもう一つの書に「病む人の気持を」というのがあります。放射線医学は無機質なものであってはいけません。 患者さんとそのご家族、検査や治療を依頼する他の診療科の医師、診療放射線技師さんや看護師さんなどのコメディカルの皆さん、病院のスタッフ、様々な人達の立場や気持ちを慮ることのできる医療人でありたいものです。 放射線科の仕事の醍醐味は、たくさんの診療科のハブとなって医療に貢献できることです。そのためには、知識や技術を常にアップデートさせることに加え、適切なコミュニケーションを取れる人間であることが大事だと思います。
人工知能(artificial intelligence [AI])が、画像診断や放射線治療の日常診療に実装されるようになりました。また、生成AIも日常生活にかなり浸透しており、多くの医療従事者の負担を軽減できるツールとなりつつあります。 AIの発展により放射線科医の仕事が脅かされるのではないかという意見を聞いてから10年以上経ちましたが、現在では多くの放射線科医は、AIを脅威と感じるのではなく、AIがもっと便利で使いやすいものになり、仕事の負担が軽減することを期待しています。 また、我々放射線科医もAIで済ますことの出来る仕事を漫然と惰性で続けていける訳ではありません。他の診療科に役立つ、淘汰されない放射線科医、新たな放射線医学を切り開いていく人材を育成することも九州大学放射線科の重要な責務だと考えています。
私が医師となってから30年が経過しました。当時を振り返ってみると、我々を取り巻く社会も放射線医学のあり方も大きな変貌を遂げました。当時は、ポケットベルで病棟から連絡を受け、シャーカステンにフィルムをかけて10㎜スライス厚のCTを読影し、 スライド作成はアナログカメラで撮影していました。医療以外の職種でも多くのことが驚くほど変貌しています。 そして、どんな職種でも同じことを漫然と続けていれば淘汰されるのは当然のことです。むしろ、医療技術の進歩をいち早く実感しながら臨床と研究が出来ることも放射線医学の魅力のひとつだと思います。 放射線科医の数は全く充足していません。放射線科医の新たな仲間がもっともっと増えてくれることを心から望んでいます。
令和7年4月
九州大学大学院医学研究院臨床放射線科学分野
教授 石神康生